どーもヨーラです。
演奏家としてそれなりの期間活動をしていると、どうしても初見で演奏しなければならない機会というのは出てきます。
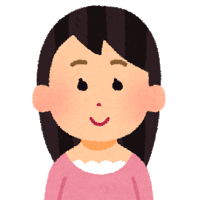
急遽この曲をやりたくなりました!
とか、
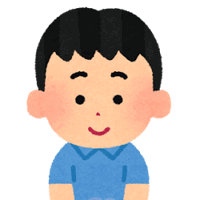
間違いで譜面がひとつ漏れてました!
とか、

やべ、1曲だけ譜面印刷するの忘れてリハに来ちゃった!
とか。これはこないだの僕です。
またリハは1回のみ、一晩で30曲近くを本番で演奏という仕事は実際に存在するので、譜面を見ながら演奏するという能力は必要になってきます。セッションホストとか歌伴もそうですね。
今回はそういう場面になったとき、限られた時間のなかで譜面を読んで行かなければなりません。その手順を書いてみようと思います。
初見で演奏するときの譜面の読み方手順
まず曲名、自分の楽器(パート)の譜面かどうか、また声部記号を確認する
すごく当たり前な気持ちになりますが、うっかり他のパートの譜面が渡されることも本当にあります。せっかく早く読めても別の人の譜面を読んでいたのではその努力がすべて水の泡です。なのでパートが書いていればそこを、また声部記号を確認すれば間違いに気付きやすいです。
ギタリストはF-CLEFを読む機会はほとんどありませんし、逆にベーシストもG-CLEFを読む機会はほとんどありません。まずこの譜面を読み進めていいのか、という確認を最初にします。
曲全体の構成を把握する
次に進行を確認します。キーを確認しつつ、例えばアタマから始まって1カッコリピート、2カッコで間奏に行ってダルセーニョでBメロに戻り、サビは落ちて繰り返しで復帰、tocodaでアウトロ行って最後リットして打ちっ放し、など。
もし途中で難しそうなユニゾンフレーズとかを発見しても、「わーここ難しそうだなー」と思いつつもここでは無視します。
コードとかフレーズとかもこの段階ではあまり気にせず、道順を確認するようなイメージです。
誤解を恐れずに言ってしまうと、自分がそこで良い演奏をすることよりも、まずはリハを円滑に進めていくことのほうが重要なので、ひとりだけ途中で迷って演奏が止まってしまったりすることのほうが問題が起こります。
自分のバンドなら最悪まだ良いですが、呼ばれて行ってる場合はスタジオ代も相手にかかっているし時間もかなり限られていますしね。
キメやユニゾンがあればそこを確認
イントロの締めとか、サビ前でキメがあったりするので、そこを最後に確認します。またユニゾンもあればそこも確認したり。ものすごく複雑なユニゾンとかがあったら、編曲者を恨みましょう。
確認できる時間は現場によりけり
曲の長さとか構成にもよりますが(人間関係や自分の立場にもよる)、ここまでで30秒から1分くらいですかねー。1分を超えてくると「まだー??」という心の声があちこちから聞こえてくるかもしれません。歌伴とかは、ボーカルの人(お客さん)は歌うだけなので、早い傾向があります。
メロやコードは弾きながら読む
平メロとかそういうところは全部弾きながら読む感じですね。僕はベースなので、ざっくりベースラインというかリズムパターンを決めつつ弾き始めます。
そこでドラムのパターンと最初から合えばラッキー、合わなければすぐに寄せちゃいます。なので事前にラインを決めるということはほぼ無意味に等しかったりします。
リハの流れでどんどん変わっていったりするので、自分のなかで決めちゃうと逆にそれが足かせにもなります。ただここはこうしたい、ということがあればそれは伝えますけどね。
遊びの要素、スペースを多めに残しておく感じですかね。家具を組み立てるときにネジを最初は仮止めにしないと、最後にうまくはまらないし。
終わりに
玉譜の読み方とかコードに対してのラインの作り方はまたちょっと別の話です。これは普段のトレーニングと引き出しによるので。でも今回書いた手順で譜面を読んでいけば、なんとかなるはずです。
譜面は結局曲の設計図みたいなものでしかないので、最終的には自分のセンスと力量によります。その設計図、骨組みに対してこれだけ肉付けのパターンを提示できますよ、的な。ではまた。




コメント